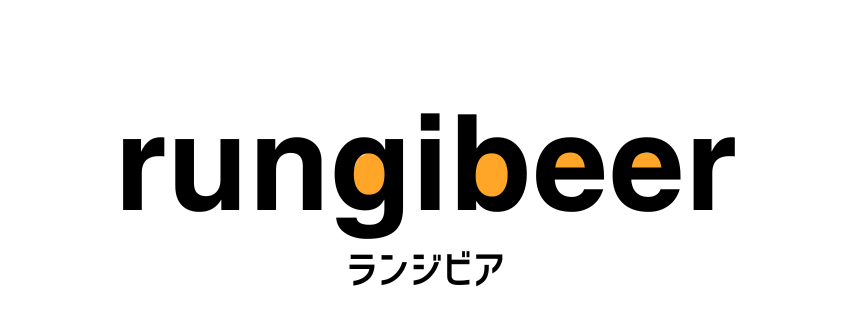哀れなるものたち。
弱い犬ほどよく吠える。
この映画を観て私が面白いと感じた箇所を深堀りして書いていく。
ストーリー自体は他の場所で専門の人がまとめているので、私はあくまで観た人との感想交換を目的として断片的に書いていこうと思う。
とんでもない傑作を観たのでしっかりと感想を残したい。
以下、ネタバレを含みます。
改行をたくさん入れるので自己防衛はお任せします。
そろそろいいかな。
ベラの衣装
ベラの衣装において気付いたことが2つある。
どうしてもこれを書きたくてこのnoteを書いている。
作中でベラの衣装は事あるごとに変わっていった。
エマ・ストーンのその着こなし具合に感嘆しながらも、序盤はパフスリーブの膨らみ具合になかなか目が慣れなかった。
膨らみどころか、肩を怒らせているようにも見えた。
パリコレのランウェイからそのまま出てきたかのような出で立ちと、そのぎこちなさや幼稚さのバランス感覚に酔ってしまった。
序盤の丁寧な背景説明も相まって、ベラのキャラクターがなんとなく掴めてきたころにはこのアンバランスな衣装もセットで脳にインプットされていた。
マックスがあまりにも美しい痴人、といった表現をしていたがまさしくその通り。
そんなベラも気付けば成長を重ね、ファンシーな色のドレスだけでなく大人っぽい色のドレスを身に着けていた。
また、パフスリーブのサイズ感にも随分と変化が見られ、シチュエーションに応じて大小様々な変遷を辿っていた。
TPOに応じた服装という見方もできるが、そのとき自身が相手に対して取っている態度・ポジションを身に着けた服で表現しているように思えたのだ。
セックスと立場
とにかくヤりまくるベラ。
食事中にきゅうりを性器に突っ込み性の悦びを覚えた初期衝動を裏切らない貪欲さだった。
セックスを通して男性から経験と精気を吸い上げ、我が物にしていくベラ。
当初はベラを子供扱いしていたダンカンも、気がつけばベラに依存し、最終的には捨てられてしまった。
豪華客船でハリーとマーサに出会ってから性の悦びよりも知の悦びに目覚め、ついていけなくなったダンカン。
少々痛々しさを感じるシーンもあったが、思春期の追体験からいたたまれなくなった。
船を降りたあと、パリで娼婦として働きはじめたベラ。
今の自分の状況を鑑みて、娼婦として働くことが合理的だということをオーナーに伝えたベラはいやに理屈っぽかった。オーナーへの売り込みというよりは自分の納得感を得るための説明だったのだろう。
このシーンを観て、脳の持ち主である赤子の性別は男性なのではないかと思った。
受け容れること
冒頭シーンで、外に出ることを拒んだだけであれだけの激しいパニックを起こしたベラ。
ゴッドの死が近いという報せを受け、パリからロンドンへ帰ってきたベラはすっかり大人になっていた。
衣装は黒。そしてパフスリーブはなく、身体に沿って落ちていた。
あのベラがTPOに合わせた服装をしている。
気持ちが沈んでいることを表現したのかもしれないが、落ち着いて、ゴッドの最期のために駆け付けた。自身の人生の中で大事な瞬間だと捉えて生活を捨てて駆け付けた。
大事なときにああいった選択ができるように育ったベラに感情が乗り過ぎた。
権威及びその象徴と脆さ
ベラとマックスの結婚式にて、ダンカンと共に現れたアルフィー。
夫として亡くなったはずの妻を連れ戻しにきた。
将軍という権威の象徴的な役に就くその男はベラを諭して城のような邸宅へ戻る。
モラハラ・パワハラの塊のような、わかりやすく全女性の敵として描かれた彼は、ことある毎に拳銃をチラつかせて自身の権威を主張する。
子供のような無邪気さで、子供のような臆病さで、現実から目を背けながらその銃口を人へ向けていた。
しかしその拳銃を用いた権威は、一度死んだベラの前では薄れた。
死よりも自由を失うことの方を恐れているベラ。
死んだ方がマシ。そういう態度が全面に出ていた。
この立ち向かう姿勢がベラの大きな魅力だ。
まとめ
フェミニズム映画だ、という評論もあるようだが私はそうは思わなかった。
性別問わず勇敢な人はいるし、被害者意識の殻から抜け出せない人もいる。
ベラは昨今のフェミニストとは違う。
搾取を叫ぶこともなければ、被害者意識もしない。
包摂されることを選ぶこともなく、本当の自由を純粋に求めて自ら道を選び切り拓いている。
私が昨今のフェミニストならば、この映画を絶賛することはないだろう。
何故なら自身の立場が危うくなるからだ。
真顔のフェミニズムが本来こういった精神性・取り組みなのであれば大いに賛同したい。
あとエッグタルト美味しそうだった。食べたい。
私がこの映画に邦題を付けるならば 弱い犬ほどよく吠える とするだろう。