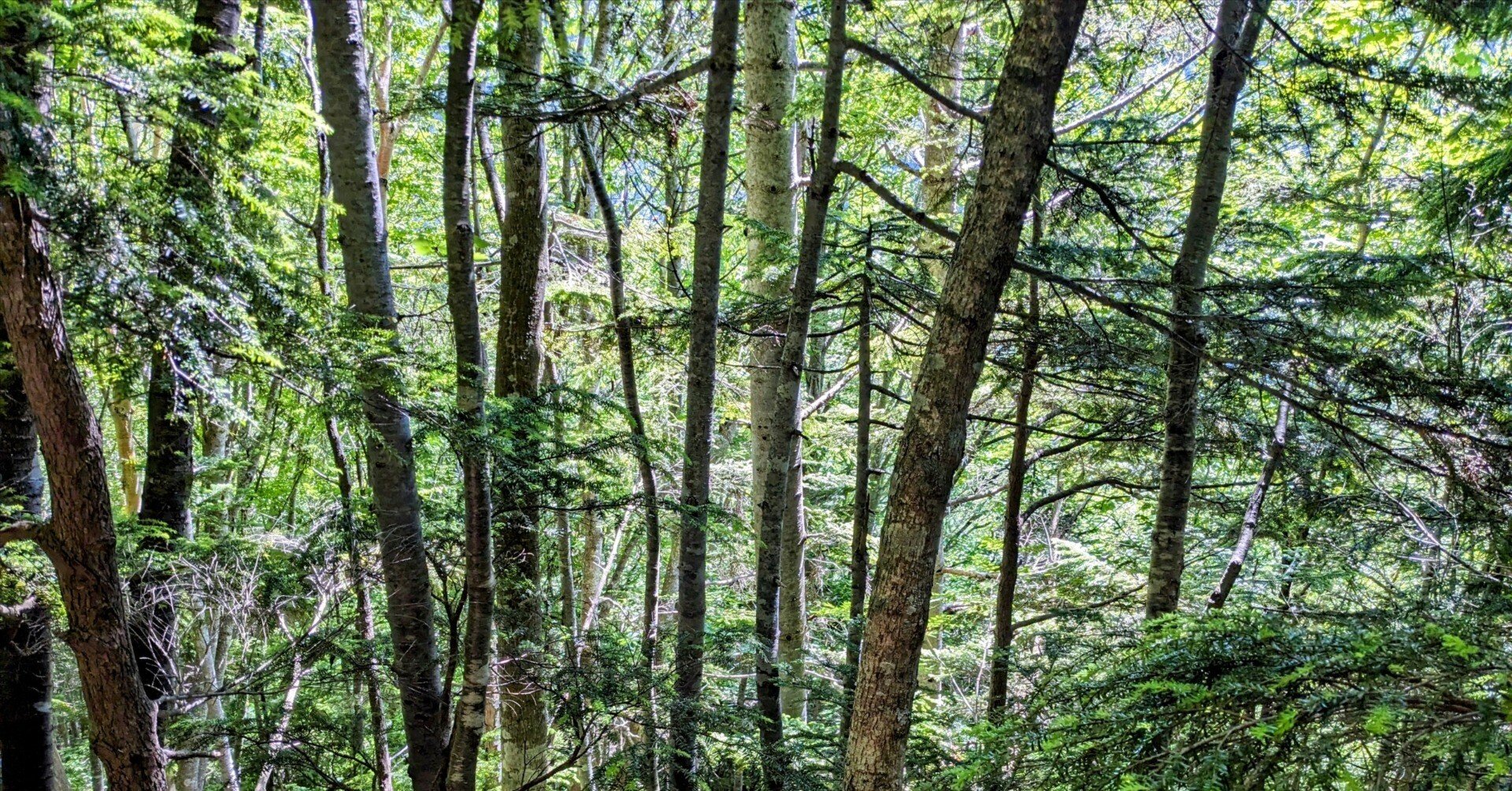
先日、妻の墓参りに行った際、お寺の掲示板にあった言葉がずっと頭の中でぐるぐるしている。
“おごらず、人と比べず、面白がって平気で生きればよい”
まったくもってその通りだ。
そうやって生きていきたい。
気に入って、先日書いた買ってよかったもの記事のタイトルにも拝借した。

毎日のように反芻して、頭に馴染んできた頃。
これは住職さんのオリジナルなのか、それともどなたかの言葉なのか。
不意に気になって検索したところ樹木希林さんの言葉であることが分かった。
樹木希林さんの葬儀の際に娘の内田也哉子さんが紹介されたようだ。
本人が直接世にはなった言葉ではなく、娘にかけた言葉が自身の葬儀で娘から紹介され、結果的に世間に広まった。
そして反響があった。
これこそが おごらず、人と比べず、面白がって平気で生きればよい を体現してきたことの証明だろう。
恥ずかしながらお寺の掲示板で出会うまではこの言葉を知らなかったが、このタイミングで知ることができてよかった。
反芻する中で、何が私に刺さったのだろうという考察に差し掛かった。
そう考える中でこれは文字に残したいと思いこの記事を書いている。
私に刺さったのはおそらく面白がって平気で生きるというフレーズだろうと考えている。
おごらない。
これは日本人に根ざした美しいとされている精神性そのもの。
承認欲求に塗れた現世では特にこの精神性の価値は上がっているだろう。
こうしてわざわざ自身の考えをnoteで世に出している私のようなものはおごっている側の存在かもしれない。
人と比べない。
まあこれも道徳心溢れるフレーズだ。
おごった上に人を卑下して悦に入るような人間は気づいたら独りぼっちだ。
とはいえライバル視等の上昇志向の過程で生まれる比較もあるし、それは好循環に繋がることがあるので一概に否定はできない。
平気で生きる。
平気っていいよね。
なるべく平気でいたい。
平気であるからこそ、動揺がスパイスになったりする。
あれ?平気ってなんだっけ。
辞書で引いてみた。
へい‐き【平気】 の解説
[名・形動]1 心に動揺がないこと。落ち着いていること。また、そのさま。平静。「何が起きても―だ」「―なふりをする」
2 気にかけないこと。心配しなくともよいこと。また、そのさま。「―でうそをつく」「君になら―で何でもいえる」
3 太陰太陽暦で二十四節気を定めるのに、冬至から始まる1年間を時間によって等間隔に分ける方法。初期の暦法。平気法。→定気 (ていき)
落ち着いた状態で生きる。
平静に生きる。
気にかけずに過ごす。
心配事なく過ごす。
揺れ動く心の機微を抑えて生きるということだろうか。
言葉の通り、額面通りに受け止めると、いささかつまらないものに思えてくる。
でもどうだろう。
この文章には面白がってというフレーズがついている。
ここで急に深みを増してくる。
面白がって平気で生きるということ。
動揺してしまう事象が起きても、気にかけずに落ち着いて過ごす。
ただ平気で生きるというと、菩薩のようなストイックさを感じてしまいハードルの高さに辟易してしまう。
面白がって平気で生きるというと、大ピンチでも世間に後ろ指をさされようと構わないという、どんと構えた精神性を感じる。
どうせ人生の本質はつらく、人間は孤独なぐらい百も承知している。
だからそれだけ余計に明るく楽しく振舞おうという決心を、私はこの十年間に持ち続け、更にその気持ちを強くしている。
遠藤周作さんのこの言葉にも近いものを感じる。
こちらの方が諦観が色濃いが、樹木希林さんの方は少々あっけらかんとした印象を受ける。
こざっぱりとした、吹っ切れた、シャープな、凛とした。
諦観ゆえのエモーショナルも味わい深いし、凛として孤独な切り口も気持ちいい。
YUKIでいうところの”しゃくしゃく余裕で暮らしたい“であり、孫悟空でいうところの”オラワクワクすっぞ“である。
時にはおごってしまうかもしれないし、人と比べてしまうかもしれない。
でも、それはそれで現代人の味だろう。
私は正しくて完璧な聖人を目指しているわけではない。
現時点ではおごらず、人と比べず、という点は至らないしそこの制限をすることのメリットを享受しきれない。
まだまだ未熟だ。
こうして文字に起こすことで、前半パートは出来ないことで構成されていて、後半パートは向かいたい方向を示していることが分かった。
自分とこの格言との間で、ベン図で被る部分と被らない部分がはっきりして、寄せていきたい部分とそうではない部分が理解できたからまた味が染み出してきた。
美味い。
自分の手が届く範囲で起こる大小様々な事象を自分事として捉えて、それらを面白がって平気で生きていきたい。
そうして過ごすことで得られる旨味を気ままに味わいたい。
日々の旨味を振り返って、にやつきたい。
その旨味を髄まで味わえば、次第におごりや人との比較から離れた境地へ行けるだろう。
おわり。

